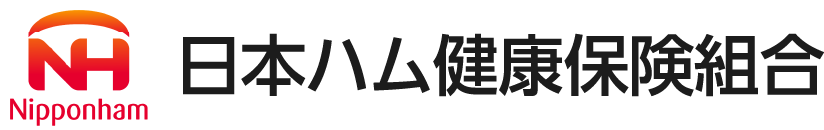家族が加入・脱退するとき
- 手続き
- 解説
- よくある質問
家族を扶養に入れたいとき
結婚・出産などにより家族が加入するときは申請が必要です。 家族が被扶養者として加入するときは、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
健康保険組合または日本ハムビジネスアソシエ(株)東京人事サービス1課までご連絡ください
| 必要書類 |
|
|---|---|
|
|
③その他認定に必要な書類
|
|
<配偶者のみ>
|
|
| 提出先 |
|
| 備考 |
マイナ保険証の利用登録を行っている場合、転職や退職等に伴うマイナ保険証利用の再登録は必要ありません。ただし、保険者(健康保険組合、共済組合等。国民健康保険に加入の方はお住まいの自治体)への届け出は、引き続き必要です。
|
家族を扶養からはずすとき
- 下記のような場合、申請が必要です。
-
- 就職・結婚・離婚・別居・死亡などにより被扶養者として該当しなくなった
- 収入が増えて、被扶養者の認定条件を満たさなくなった
- 仕送りをやめて生計維持関係がなくなった
健康保険組合または日本ハムビジネスアソシエ(株)東京人事サービス1課までご連絡ください
| 必要書類 |
|
|---|---|
<配偶者のみ>
|
|
|
<就職の場合> 健康保険加入日(資格情報)のわかる書類 (資格確認のお知らせ、資格確認書等) |
|
| 提出先 |
|
| 備考 |
マイナ保険証の利用登録を行っている場合、転職や退職等に伴うマイナ保険証利用の再登録は必要ありません。ただし、保険者(健康保険組合、共済組合等。国民健康保険に加入の方はお住まいの自治体)への届け出は、引き続き必要です。
|
健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを被扶養者といいますが、被扶養者の範囲は法律で決められています。
被扶養者の範囲
被扶養者となるためには、原則として国内に居住していて、主として被保険者の収入によって生活していることが必要です。扶養の程度の基準としては、被扶養者となる人の年間収入が130万円未満(対象者(被保険者の配偶者を除く)が19歳以上23歳未満※の場合は150万円未満、60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円未満)で、被保険者の収入の2分の1未満であることとされています。さらに別居の場合は、主としてその家族を経済的に扶養していること、定期的(毎月)かつ継続的(最低3カ月以上)に仕送りの事実があることが必要です。
また、被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
- ※19歳以上23歳未満の年齢要件の判定については、所得税法上の取り扱いと同様、その年の12月31日時点の年齢で判定いたします。(注:年齢は民法上、誕生日の前日に加算されるため、誕生日が1月1日の方は12月31日において年齢が加算されることにご留意ください。)
| 被保険者と同居でも別居でもよい人 | 被保険者と同居が条件の人 |
|---|---|
|
|
被扶養者認定における国内居住要件
2020年4月より、健康保険の被扶養者認定の要件に、国内居住要件が追加されました。日本国内に住所を有していない場合、2020年4月1日以降は、原則として被扶養者の認定はされません。(海外留学等、一定の例外あり)
国内居住要件の考え方
住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。
- ※住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。
国内居住要件の例外
外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。
【国内居住要件の例外となる場合】
- ①外国において留学をする学生
- ②外国に赴任する被保険者に同行する者
- ③観光、保養またはボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
- ④被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
- ⑤①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
国内居住者であっても、被扶養者と認められない場合
医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません。
経過措置
国内居住要件の追加により被扶養者資格を喪失する方が、施行日(2020年4月1日)時点で国内の医療機関に入院している場合、経過措置として、入院期間中は資格が継続されます。
パート・アルバイトの方の社会保険適用拡大
1週の所定労働時間および1月の労働日数が常時雇用者の4分の3以上ある場合は被保険者となります。また、4分の3未満の場合でも下記の5つの要件をすべて満たした場合、健康保険の被保険者となります。
被扶養者であるご家族が勤務先で健康保険に加入する場合は、すみやかに扶養削除の手続きをしてください。
- (1)1週の所定労働時間が20時間以上であること
- (2)雇用期間が2ヵ月を超えて見込まれること
- (3)月額賃金が8.8万円以上であること
- (4)学生でないこと
- (5)常時51人以上の被保険者を使用する企業に勤めていること
(労使合意した従業員数50人以下の会社に勤める人も対象になります。)
三親等内の親族とは?
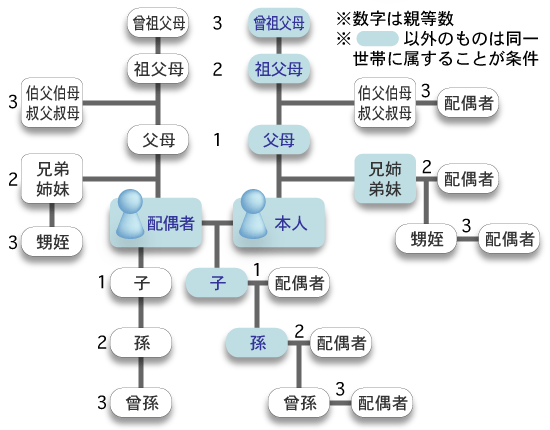
外国人の扶養認定基準
日本に居住している外国籍の女性(または男性)
国籍にかかわらず、外国籍の方の扶養認定基準は、続柄や収入等日本人の場合と基本的に同様です。
ただし、下記の2項目を満たす必要があります。
- (1)国内に居住し、住民登録をしていること
- (2)在留期間が1年以上であること(短期滞在ではないこと)
- ※在留資格が短期滞在の場合は、生活基盤を移したものと認められない一時的な状態であることから、被扶養者として認定しません。
海外に居住している場合
保険給付は、日本国内の医療を前提としているため、原則として海外居住者は被扶養者として認定しません。
ただし、次のような一時的な滞在と認められる場合は被扶養者として認定します。
- (1)被保険者の海外出向・駐在に帯同して海外に居住する場合
- (2)短期(概ね1年以内)の海外滞在
- (3)被扶養者が海外留学を行う場合
- (4)海外赴任者が現地で結婚した場合(配偶者および子に限る)
- ※いずれの場合も、国籍は問わず、被保険者により生計が維持されていることが必要です。
- ※海外で診療を受けた場合は海外療養費支給制度を利用してください。
もっと詳しく
- 被扶養者の資格確認調査(検認)開く
-
健康保険法施行規則第五十条および、厚生労働省の通知に基づき、皆様よりお預かりしている保険料を、適正な保険給付につなげる大切な調査です。調査の結果、認定基準を満たしていないと判定した場合は、事由発生日または、当健康保険組合が定めた日をもって扶養削除となります。
削除日以降に当組合の健康保険を利用された場合は、医療費の返還を求めることになりますのでご留意ください。
ご理解の上、ご協力賜りますようお願いいたします。
①ご家族の扶養状況確認調査
過去にご家族が被扶養者として認定された時の年収等の状況が、現在も維持されていることを確認する為の調査です。
【対象者】
認定基準を確認する必要があると判断する被扶養者
②夫婦共同扶養調査
当健保組合に加入していない配偶者の収入を確認する為の調査です。
子どもを夫婦が共同で扶養している場合、いずれか収入が多い方の被扶養者となるため、ご夫婦の収入を比較する必要があります。
【対象者】
当健康保険組合に加入していない配偶者
- 家族と離れて暮らすとき開く
-
同一世帯を解消し別居となる場合は、主としてその家族を経済的に扶養していることが継続されていなければ、被扶養者の資格を継続することはできません。経済的扶養の解消事実発生後、すみやかに扶養削除の手続きをお取りください(別居家族の経済的扶養の詳細は、被扶養者の範囲をご覧ください)。
別居者の経済的扶養の確認は、毎年執り行う「被扶養者現状調査」にて仕送りの有無、金額等を確認いたします。
- 被保険者・被扶養者が75歳になった場合開く
-
2008年4月から後期高齢者医療制度が創設され、75歳以上(寝たきり等の場合は65歳以上)の人はすべて後期高齢者医療制度に加入することになりました。
したがって、被保険者が75歳になった場合、被保険者が健康保険組合の加入資格を失いますので、被扶養者も同様に健康保険の加入資格を失い、他の医療保険に加入しなければならなくなります。また、被扶養者自身が75歳になった場合も、後期高齢者医療制度の加入者となりますので、健康保険組合の加入資格を失います。
- 夫婦共働きの場合の子の扶養開く
-
夫婦ともに収入があり共同で子を扶養する場合、被扶養者となる人の人数にかかわらず、原則どちらか年間収入の多い方の被扶養者となります。
また、夫婦それぞれの年間収入が同程度の場合は、主として生計を維持する方の被扶養者となります。